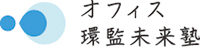【保健師・環監向け】災害時の衛生・防災先進国イタリアから学ぶ
【防災先進国イタリアから学ぶ】
1 イタリア防災の特徴
2 イタリア防災に学ぶ点
3 被災地のダメージエリア
4 SUM基準、その他
5 環監の視点(市民の命・健康をまもる)
6 災害時の衛生・研修講座ご案内
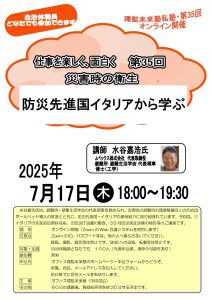
元文京区文京保健所・環境衛生監視員で、『災害時・避難所の衛生対策のてびき』著(根本昌宏監修、一般財団法人日本環境衛生センター)、避難所の衛生対策・レジオネラ症対策の研修講師をしている「オフィス環監未来塾」中臣昌広です。
2025(令和7)年7月なかば、第35回環監未来塾私塾・オンライン無料講演会を開催しました。
テーマは、「災害時の衛生 防災先進国・イタリアを知る」です。
講師は、避難所・避難生活学会の代表理事、Jパックス株式会社・代表取締役、水谷嘉浩氏です。
全国の保健所・保健師、環境衛生監視員など、約60名の皆様が参加されました。
ご講演では、イタリアの先進的な災害時対応、能登半島地震での段ボールベッドの導入、わが国の防災庁設置の動き、3月に実施された防災実証訓練などの話がありました。
参加者の声で、「イタリアが先進的と聞いたことがあったが、具体的なことを知らなかったのでとても参考になりました」「日本でもイタリア式で訓練を始めていることを初めて知れたので良かった」とありました。
今回は、講演時におこなわれた水谷嘉浩氏と参加者との質疑応答から、有用な情報をご紹介します。
1 イタリア防災の特徴
(質問)日本との違い
日本と海外の防災対応で、一番大きな違いを知りたいです。
(回答)
防災専門の省庁があるか、ないかです。
わが国でも、いま防災庁設置が進められていますが。
(質問)TKB48の根拠
TKB(トイレ・キッチン・ベッド)48時間以内に・・・の48時間以内の根拠を教えてください。
(回答)
イタリアの発災2日以内の活動を参考にしています。
避難所での災害関連死を防ぐためです。実際、イタリアでは災害関連死はあり得ないと言います。
イタリアでは、被災自治体ではなく、近隣自治体が主体になって活動します。
(質問)防災先進国
イタリア以外の国で、防災が進んだ国はありますか。
(回答)
イタリアが、とびぬけていると思います。
台湾で大きな地震があった後、調査に行ったとき、仏教団体、自治体が主体で取り組んだことを知りましたが、広域な仕組みや標準化はありませんでした。
アメリカでは、FIMAの防災対応組織があります。
(質問)災害支援の哲学
災害支援の哲学について、現地の方とお話された具体的な内容を知りたいです。
(回答)
イタリアでは、準備をしっかりした上で、災害規模に応じて、柔軟に対応しています。
ルールにのっとってやるだけではなく、前例にとらわれず対応しています。
災害時の衛生対策、避難所・避難生活の衛生対策のご質問、ご相談など、お気軽にお問い合わせください
災害時の衛生対策、避難所・避難生活の衛生対策の講師ご依頼につきまして、お気軽にお問い合わせください
2 イタリア防災に学ぶ点
(質問)ボランティアの費用
イタリアのボランティアは、有償でしょうか。
(回答)
イタリアのボランティアは、たとえば、電気工事、水道配管工事、調理など各分野の職能ボランティアをさします。ボランティアとは本来「志願者」と言う意味です。
職能ボランティアは、一定期間の研修期間を修了することが必要です。
国民の20人に1人が登録されているといわれています。
職能ボランティアは、個人が特別な報酬をもらえるわけではありませんが、避難所支援中も会社やレストランなどの雇用主から普段通り給料は支払われます。
国から、雇用主へ、人件費が支払われます。
災害支援を申し出たボランティアについて、雇用主が拒否できない仕組みです。
災害支援にいく人について、ケガや病気などが補償されます。トラブル補償もあります。
自分の時間と労力を提供する仕組みです。
経費は出ます。
避難者と一緒に避難所に滞在して、共同生活をしながら支援活動します。
(質問)職能ボランティアの職種
民間の専門職種としてどのような職種がありますか。どのような職種を組み合わせて行くことが必要でしょうか。
(回答)
職種は、医療福祉、心理学の専門家、料理人、大型車運転手、重機の運転手、電気や水道工事などのエンジニア、動物の専門家など多種にわたります。
TKBに必要な専門職として、トイレ掃除者もいます。
職能ボランティアは、トレーニングを受けて認証がされます。
コックさんは、60時間の研修があります。
被災者支援のため、あらゆる職種が必要との考えがあります。
3 被災地のダメージエリア
(質問)障がい者の福祉避難所
障がい者の福祉避難所はありますか。
(回答)
イタリアでは、避難所での生活が困難である場合は専門施設に広域搬送することがあります。
災害時に、避難所を被災したダメージエリアにつくらないことが基本になっています。
たとえば、津波被害では、粉じんの影響のないところに避難所がつくられます。
(質問)交通手段が途絶えたとき
拠点避難所に設備を持ち込むとのことですが、その際交通手段が途絶えて設置が遅れてしまうというようなことはないのでしょうか。
(回答)
避難所を、被災したダメージエリアにつくらないことが大切です。
被災者をダメージエリアの外の安全な場所まで出すのです。
いろいろな考えがあり、ほかに行きたくない住民のかたもいるかもしれません。
イタリアでは、ダメージエリアを立入禁止にします。
なぜできるのか。非常事態宣言が、地方の首長の権限にあるからです。
ダメージエリア外の安全な避難所から毎日、バスの送迎があり、自宅かたづけが可能になっています。
日本では、ライフラインが途絶えたダメージエリアにある避難所に一定数いるケースがあります。
(質問)ダメージエリア外への人の移動
ダメージエリア外の安全な地域に避難所を設置するということは、人を移動させるイメージなのでしょうか。日本で被災者が、避難所で生活しながら、自宅の片付けに行くということがありましたが、イタリアでは、被災者は自宅を、どのように復旧がされていくのでしょうか。
(回答)
イタリアでは、バスで送迎がされます。
避難先は、ホテル避難(借上げ、リゾートホテル)、(5~6人が生活できる)テントです。
家の片づけのため、ホテルから毎日、送迎バスで自宅エリアへ行くことができます。
物流が途絶えることはありません。
日本でのこれからの訓練では、安全な場所への長期避難を、できるだけ近いところにすることが大切です。
例では、能登半島のケースでは、金沢があたると思います。
ダメージエリアでは、建物の倒壊や道路の損壊などで、物流が通常のようにいきません。
ダメージエリアから外へ移動することが大切です。
短期避難場所として、家が大丈夫で、地震への不安で地元避難所にいるケースはあるでしょう。
ライフラインが途絶えたことで避難所にいる短期避難者と、家屋の損壊のために長期避難を余儀なくされた避難者を切り分ける必要があります。
4 SUM基準、その他
(質問)SUM基準
SUM基準は、水谷先生の発案・提唱ですか。
(回答)
そのとおりです。イタリアに学び、被災地を支援する避難所関連の、Standard 標準化、Unit ユニット化、Mobile 機動力の三つを提唱しています。
(質問)防災教育
わたしは大学で教員をしていますが、教育として何かすべきこと、できることはあるでしょうか。
(回答)
教育のなかに、防災を組み込んでいくのが必要だと思います。
25の災害の500カ所の避難所を見ました。
社会の弱者がダメージをうける、それが避難所です。
ある自治体の防災訓練で、地域の専門職、料理人に中学校に来てもらい、避難所の食事をつくってもらいました。
段ボールベッドの組立をする、子どもたちの訓練を毎年つづけているところもあります。
継続した若者や子供達への防災教育が地域の防災力の強化につながります。
(質問)建物の耐震
イタリアでは、家の耐震とかはどうなっているでしょうか。
(回答)
イタリアでは、耐震基準がありますが、歴史的建造物は、天井が落ちやすいと考えられます。
フィレンツェ市役所は、1200年代の800年前の建物です。
ローマだけではなく、旧市街の建物はレンガ、石の積み上げの壁で、地震によわく、崩れやすいと思われます。
5 環監の視点(市民の命・健康をまもる)
災害発生時に守られた命を、どのような状況にあっても、避難所・避難生活で失うことがあってはならないと思います。
そのために、何が最善かを考える必要があると思います。
ダメージエリアに避難所をつくらない。命をまもる手段・方法が、そこにあるように感じました。
私は、1995年に、阪神・淡路大震災1カ月後の神戸市や西宮市などの被災地内の避難所を訪れたとき、断水と密な避難スペースなど劣悪な環境を目にして、同じような考えをもち、その提言を専門誌に寄稿したことがあります。
被災地のダメージエリアからの、地域ごとの一時的、集団避難が、生活者の命・健康を守ることにつながっていると感じたのです。
災害時の衛生対策、避難所・避難生活の衛生対策のご質問、ご相談など、お気軽にお問い合わせください
災害時の衛生対策、避難所・避難生活の衛生対策の講師ご依頼につきまして、お気軽にお問い合わせください
『災害時・避難所の衛生対策のてびき』ご購入をお考えのかたは、こちらから注文ができます。
【ご案内】
【2025(令和7)年度講座】
2025(令和7)年度のオフィス環監未来塾の研修講座の写真入り詳細をご覧いただけます。
【2026(令和8)年度講座】
2026(令和8)年度のオフィス環監未来塾の研修講座の写真入り詳細をご覧いただけます。
・環監業務の悩み、課題がありましたら、ご相談をお受けしています。
・課題の解決につながる講座をご用意しています。
・保健師の皆様への研修のご相談、避難所の衛生対策活動等のご相談をお受けしています。
月に数回、環監のための、レジオネラ症対策、防災、仕事術、講座情報など、最新情報をメールで真っ先にお届けします。ご希望される場合、こちらにご記入ください。
【活動実績】
(本・図書・出版物)
・2025年、介護保険専門紙『シルバー新報』(環境新聞社)で「介護現場のBCP 災害時の知識」を連載中です。
・2025年、月刊誌『クリンネス』(イカリホールディングス株式会社)で「衛生視点で感染症・災害時のBCPを考える」を連載中です。
・2022年、本『災害時・避難所の衛生対策のてびき』根本昌宏監修(一般財団法人日本環境衛生センター)を出版しました。
・2021年、専門誌『生活と環境』(一般財団法人日本環境衛生センター)で「災害時の居住環境 ~保健所・環境衛生監視員の視点から~」を連載しました。
・2020年、『災害時の保健活動推進マニュアル』(日本公衆衛生協会・全国保健師長会、令和2年3月)で「生活環境衛生対策」(避難所の環境衛生管理アセスメント)を分担執筆しました。
(活動)
被災地の地元自治体に協力して避難所の衛生対策活動・調査をしました。
・2024年、能登半島地震(石川県、珠洲市、七尾市)
奥能登豪雨(石川県、珠洲市)
・2019年、令和元年台風19号(長野市、いわき市)
・2018年、西日本豪雨(倉敷市)
・2016年、熊本地震(熊本市)
・2011年、東日本大震災(気仙沼市)
(調査活動)
・1995年、阪神・淡路大震災
(講師)
・2025年、神奈川県公衆衛生協会平塚支部講演会「災害時の公衆衛生活動、~災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策、保健所・環境衛生監視員の視点から~」
・2025年、豊田市役所研修「災害時の避難所等における衛生対策に関する研修」
・2025年、豊橋市保健所研修会「災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策 ~避難生活で健康を守るポイント~」
・2025年、日本災害食学会・災害食専門員研修会「災害時の水の安全・衛生」
・2024年、神奈川県公衆衛生学会「シンポジウム・避難所における健康危機管理」
・2024年、宮城県気仙沼圏域研修「災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策 ~保健所・環境衛生監視員の視点から~」
・2024年、宮城県登米地域災害対応研修「災害時における環境衛生対策」
・2024年、愛知県看護協会・研修会「災害時の生活環境衛生対策の課題と実際」
・2024年、福井県嶺南地域保健・福祉・環境関係職員研修「災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策 ~保健所・環境衛生監視員の視点から~」
・2024年、鳥取県市町村保健師協議会研修会「災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策 ~保健所・環境衛生監視員の視点から~」
・2024年、全国保健師長会、能登半島地震関連・緊急オンライン研修会「地震断水時の避難所・避難生活の衛生対策」
・2023年、令和5年度 兵庫県・北播丹波ブロック市町保健師協議会・研修会「災害時の避難所の衛生、感染症対策」
・2023年、第54回 沖縄県衛生監視員研究発表会及び研修会・特別講演「災害時・避難所の衛生対策について」
・2022年、国立保健医療科学院、令和4年度 住まいと健康研修「災害時の公衆衛生活動」(オンライン)
・2022年、東京都特別区職員研修所、令和4年度専門研修「地域保健」(主に保健師対象)「災害時の避難所の衛生・感染症対策、保健所・環境衛生監視員の視点から」
(学会)
・2025年、第30回日本災害医学会総会・学術集会「サーモグラフィ画像を活用した避難所の環境衛生管理」
・2025年、第52回建築物環境衛生管理全国大会「能登半島地震被災地の公衆衛生活動者を支援するためのIT活用の成果」
・2023年、日本防菌防黴学会・第50回年次大会「令和4年台風第15号による大雨被災地の泥から検出されたレジオネラ属菌について」
・2021年、日本防菌防黴学会・第48回年次大会(オンライン開催)「令和元年東日本台風(台風19号)被災地の泥から検出されたレジオネラ属菌について」
・2021年、第48回建築物環境衛生管理全国大会(オンライン開催)「令和元年東日本台風(台風19号)被災地の避難所の施設・空気環境の実態」奨励賞受賞
・2020年、第79回日本公衆衛生学会総会(オンライン開催) 「令和元年台風19号被災地の避難所における空気環境等の実態」
・2012年、第39回建築物環境衛生管理全国大会「東日本大震災被災地の避難所の施設・空気環境の実態」最優秀賞受賞