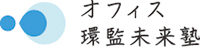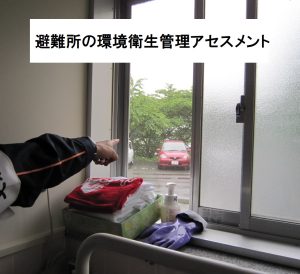【環監・保健師向け】レジオネラ対策・配管の高濃度塩素消毒
【配管の高濃度塩素消毒】
1 レジオネラ症防止指針等の内容
2 高濃度塩素消毒の効果
3 高濃度塩素消毒の実際
4 環監の視点(衛生管理に近道はない)
5 レジオネラ研修講座ご案内

こんにちは。元文京区文京保健所・環境衛生監視員で、『レジオネラ症対策のてびき』著(倉文明監修、一般財団法人日本環境衛生センター)、レジオネラ症対策・避難所衛生対策の研修講師をしている「オフィス環監未来塾」中臣昌広です。
先日、A自治体の保健所・環境衛生監視員から施設向け「レジオネラ対策講習会」講師のご依頼がありました。
そのとき、施設への指導・助言で悩んでいるのが、週に1回の配管の高濃度塩素消毒だとありました。
各施設で、実施がされていなかったり、そもそも高濃度塩素消毒が何かを理解していなかったりしている状況とのことです。
こうした悩みを解消するため、レジオネラ対策の配管の高濃度塩素消毒について、私が理解する内容を整理してみたいと思います。
下記の記述は、専門家の株式会社ヘルスビューティ・シニアテクニカルアドバイザーの藤井明氏のご意見を参考にしました。
ご活用ください。
1 レジオネラ症防止指針等の内容
レジオネラ対策の技術的な根拠となっている『第5版 レジオネラ症防止指針』(公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター)、他の資料を読み、私が理解した内容は次のとおりです。
浴場施設のレジオネラ汚染の防止策のなかに、維持管理の防止策として配管の洗浄・消毒があります。
配管の洗浄・消毒の目的は、配管内のバイオフィルム(生物膜)の除去です。
配管内で湯水が滞留すると、バイオフィルムを形成しやすくなるからです。
バイオフィルムが成長しない段階で、抑制や除去をするのがレジオネラ症対策として効果的です。
配管の洗浄・消毒として挙げられているのが、二つあります。
(1)年1回以上の薬剤による化学洗浄
過酸化水素、過炭酸ナトリウム、高濃度塩素などが用いられます。
専門業者に依頼すると、半日あるいは1日の単位で、配管の系統ごとに作業がおこなわれます。
(2)週1回以上の生物膜等の除去
浴槽の水位を計る検知管や、男女の浴槽の一定の水位を保つための連通管について、週に1回以上、高濃度塩素などを配管内に注入して洗浄・消毒します。
レジオネラ症を予防するために必要な措置 に関する技術上の指針(平成15年、厚生労働省)には、入浴設備の維持管理上の措置として、次の記述があります。
<ろ過器内は、湯水の流速が遅くなり、最も生物膜や汚れ等が付着しやすい場所であるため、一週間に一回以上、ろ過器内に付着する生物膜等を逆洗浄等で物理的に十分排出すること。併せて、ろ過器及び浴槽水が循環している配管内に付着する生物膜等を適切な消毒方法で除去すること。>
文面から、週1回以上、消毒により配管内の生物膜等を除去することが読み取れます。
※年に1回以上の配管洗浄だけでは必ずしも十分な対策とはいえないため、週に1回以上の高濃度塩素消毒を組み合わせることで、循環配管の清浄度を高いレベルで維持することが可能になります。
【レジオネラ症対策を学ぶ連続講座】では、配管洗浄(浴槽水)の作業工程の動画を見ながら、解説を詳しく聞くことができます。
ご活用ください。
レジオネラ症対策のご質問、ご相談など、お気軽にお問い合わせください
レジオネラ症対策の講師ご依頼につきまして、お気軽にお問い合わせください
2 高濃度塩素消毒の効果
(高濃度塩素消毒の目的)
配管内のバイオフィルムの付着が少ないうちに除去し、定着を防ぐものです。
配管洗浄の間隔を延長できる可能性があるともいわれています。
(注意点)
浴槽水の水質検査結果や入浴者数に応じて、塩素濃度を高くしたり、実施頻度を上げたりして、現場の状況に合わせて適切に実施します。
(効果例)
藤井明氏の配管内のファイバースコープ画像の解説を聞いて、こう理解しました。
1年に1回の配管洗浄のあと、毎日の塩素消毒を実施し、高濃度塩素消毒を実施しない場合、2カ月半後に配管内部にバイオフィルムの付着が認められました。
一方、毎日の塩素消毒とともに、週に1回、高濃度塩素消毒を実施した場合、2カ月後に配管内部に画像で確認できるバイオフィルムの付着は、ほとんどありませんでした。
高濃度塩素消毒の実施により、配管内部の清浄度を維持しやすくなったことが伝わってきました。
(泡の発生)
高濃度塩素消毒の実施中、配管中のバイオフィルムの剥離にしたがい、浴槽水の水面に泡が発生し、泡が消えにくいことがあります。
泡が多量に発生していると認められる場合、高濃度塩素消毒実施の間隔を短くするか、濃度を高めにするか、したほうがいいかもしれません。
配管洗浄の実施を検討するのも選択肢のひとつです。
別ページに、浴槽水の汚れと泡の関係を記述しています。
3 高濃度塩素消毒の実際
詳しくは、『レジオネラ症対策のてびき』中臣昌広著・倉文明監修(一般財団法人日本環境衛生センター)のP36に掲載しています。
高濃度塩素消毒の濃度は、通常、5~10 mg/L を指します。
浴槽水の残留塩素濃度を 0.4 mg/L とすれば、10~20倍以上の濃度になります。
手順は、次のとおりです。
(1)準備する浴槽水
営業時間が終わったあと、浴槽の湯を排水する前におこなうとよいでしょう。
換水前の浴槽水は、水位を循環ができるところまで下げると、塩素量の負担を軽減できます。
(2)塩素剤の投入
湯の中、あるいはふだん塩素剤を投入している箇所に塩素剤を加えます。
濃度を 5~10 mg/L にします。
投入量の例:
次亜塩素酸ナトリウム(液体、有効塩素12%、比重1.2)を使う場合を考えます。
投入量(mL)=目標塩素濃度(mg/L)×水量(t)×100÷有効塩素濃度(%)÷比重
目標塩素濃度 5mg/L、浴槽水・配管の水量 10t、塩素消費がないとして計算します。
= 5 mg/L × 10t × 100 ÷ 12% ÷ 1.2
≒ 347 mL
投入量は、約347 mL になります。
※実際には、浴槽水や配管の汚れなどによる塩素消費があるので、計算量の 1.5~2 倍を目安に投入するのがいいといわれています。
(3)配管の循環
1~2時間、循環します。
(4)逆洗、排水
ろ過器の種類により、逆洗浄のあと、排水します。
(5)塩素濃度の測定
濃度を確認するとき、測定器の濃度範囲が 0~2 mg/L の場合があります。
そのときは、蒸留水などで10倍にうすめると、 5~10 mg/L を測定することができます。
蒸留水のかわりに、水道水を浄水器に通した、塩素のない水を使用してもいいでしょう。
こうした高濃度塩素消毒を週に1回、実施することで、バイオフィルム(ぬめり)の形成を抑えることにつながるのです。
ただし、高濃度塩素は、配管等の材質によっては、サビ・腐食の原因となるかもしれません。
排水後、浴槽に水や湯を張って、循環すると安心でしょう。
なお、別ページに、残留塩素濃度測定の解説の詳細が掲載されています。
4 環監の視点(衛生管理に近道はない)
高濃度塩素消毒の詳細を調べていくと、レジオネラ症対策の衛生管理に近道はないと感じました。
毎日、毎週、毎月、毎年の定期的な衛生管理をするという、地道な取り組みが大切だと思います。
そのなかで、今回は、高濃度塩素消毒を取りあげました。
配管中は、目視ができない空間だけに、週に1回、高濃度塩素消毒を実施して、どれだけの効果があるのか、営業者に実感してもらえないのが環監にとって悩みのタネかもしれませんね。
施設で高濃度塩素消毒を実施したとき、浴槽の水面に泡の発生や、消えにくい泡があるかを尋ねてみてはどうでしょうか。
「ある」と答えがあったとき、実際に現場を確認して、高濃度塩素消毒の濃度を高めたり、頻度を上げたりする助言ができる可能性があります。
場合によっては、配管洗浄の実施につなげることができるかもしれません。
【レジオネラ症対策を学ぶ連続講座】では、配管洗浄(浴槽水)の作業工程の動画を見ながら、解説を詳しく聞くことができます。
ご活用ください。
レジオネラ症対策のご質問、ご相談など、お気軽にお問い合わせください
レジオネラ症対策の講師ご依頼につきまして、お気軽にお問い合わせください
【ご案内】
【2025(令和7)年度講座】
2025(令和7)年度のオフィス環監未来塾の研修講座の写真入り詳細をご覧いただけます。
【2026(令和8)年度講座】
2026(令和8)年度のオフィス環監未来塾の研修講座の写真入り詳細をご覧いただけます。
『レジオネラ症対策のてびき』の概要はこちらから確認できます。ご購入をお考えのかたも、こちらから注文ができます。
・環監業務の悩み、課題がありましたら、ご相談をお受けしています。
・課題の解決につながる講座をご用意しています。
・保健師の皆様への研修のご相談、避難所の衛生対策活動等のご相談をお受けしています。
月に数回、環監のための、レジオネラ症対策、防災、仕事術、講座情報など、最新情報をメールで真っ先にお届けします。ご希望される場合、こちらにご記入ください。
【活動実績】
(書籍・図書)
・2024年、専門誌『設備と管理』(オーム社)に「冷却塔の清掃方法とレジオネラ症 保健所・環境衛生監視員の視点から」を執筆しました。
・2023年、専門誌『設備と管理』(オーム社)に「老舗旅館の大浴場、湯の入れ換えが年2回 レジオネラ症対策を再考する」を執筆しました。
・2015年、専門誌『生活と環境』(一般財団法人日本環境衛生センター)に「公衆浴場・温泉・旅館業・スポーツ施設・介護保険施設のための 続・よくわかるレジオネラ症対策」を連載しました。
・2013年、『レジオネラ症対策のてびき』倉文明監修(一般財団法人日本環境衛生センター)を出版しました。
(活動)
・2024年、厚生労働科学研究費補助金(健康安全・危機管理対策総合研究事業)「公衆浴場の衛生管理の推進のための研究」の研究協力者として活動しました。
・2024年、厚生労働省のレジオネラ対策のページに掲載されている「入浴施設の衛生管理の手引き(令和4年5月13日)」改定検討の研究協力者として、元神奈川県衛生研究所・黒木俊郎先生らと共に活動しました。
・2022年、「入浴施設の衛生管理の手引き(令和4年5月13日)」の作成ワーキンググループのメンバーに、国立感染症研究所・倉文明先生らと共になりました。
・2017年、広島県三原市の公衆浴場施設で起きたレジオネラ症集団感染事例において、現地の三原市で次のとおりご協力しました。
①行政の対応強化(職員研修会の開催、対策指針・対策事業の提案など)
②管内施設の衛生管理徹底(レジオネラ症対策講習会の開催、講習会後の個別相談など)
③事故発生施設への対応(現地調査・事故の原因究明の協力、改善方法の検討など)
(講師)
・2025年、石川県南加賀保健所、入浴施設衛生管理研修会「公衆浴場、旅館、ホテル等入浴施設のレジオネラ症対策」
・2025年、鹿児島市保健所、レジオネラ症感染防止研修会「入浴施設におけるレジオネラ症感染防止対策」
・2025年、港区みなと保健所、衛生講習会「レジオネラ症対策について」
・2024年、大分県 レジオネラ症発生防止対策研修会「入浴施設のレジオネラ症発生防止対策について」
・2024年、宮崎県・宮崎市、施設向け令和6年度レジオネラ属菌汚染防止対策講習会「公衆浴場・旅館・ホテル・福祉施設・医療施設等の入浴設備の衛生管理」
・2024年、(公財)青森県生活衛生営業指導センター、公衆浴場・旅館・ホテル等施設向けレジオネラ症発生予防対策研修会「レジオネラ症対策の基礎知識と入浴施設の衛生管理の方法」
・2022年、国立保健医療科学院、令和4年度・環境衛生監視指導研修で「環境衛生監視指導の実際、公衆浴場のレジオネラ症対策」(オンライン)
・2021年、高知県、令和3年度入浴施設におけるレジオネラ属菌汚染防止対策講習会・環境衛生監視員を対象とした現場研修会「循環式浴槽立入検査の実際について」
(学会)
・2024年、第83回日本公衆衛生学会総会で、「レジオネラ症対策現場研修会の公衆衛生人材育成の成果」を発表しました。
・2023年、日本防菌防黴学会・第50回年次大会で、「令和4年台風第15号による大雨被災地の泥から検出されたレジオネラ属菌について」を発表しました。
・2021年、日本防菌防黴学会・第48回年次大会(オンライン開催)で、「令和元年東日本台風(台風19号)被災地の泥から検出されたレジオネラ属菌について」を発表しました。
・2012年、第56回生活と環境全国大会で、「文京区における公衆浴場等シャワー水のレジオネラ症発生防止対策の成果」を発表し、最優秀賞を受賞しました。