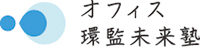【環監・保健師向け】酷暑期・避難所の熱中症対策
2025(令和7)年8月中旬、青森県の弘前大学で開催された酷暑期避難所演習に参加しました。
テーマのひとつが熱中症対策です。松本孝朗氏(中京大学スポーツ科学部教授)のご講演がありました。
避難所の熱中症対策は夏季の大きな課題ですので、過去の対策記事を一部加筆修正して再掲載します。
【酷暑期】避難所の熱中症対策
1 酷暑期避難所演習
2 暑さ指数(WBGT)
3 熱中症の症状と対処
4 症例
5 避難所の熱中症対策
6 熱中症対策の資料
7 環監の視点

元文京区文京保健所・環境衛生監視員で、『災害時・避難所の衛生対策のてびき』著(根本昌宏監修、一般財団法人日本環境衛生センター)、避難所衛生対策・レジオネラ症対策の研修講師をしている「オフィス環監未来塾」中臣昌広です。
熱中症対策は、災害時の避難所・避難生活の衛生対策に有用ですので、ご講演から、私が理解した点をご紹介します。
別ページに、能登半島地震関連の【保健師活動】避難所・避難生活の熱中症対策があります。
1 酷暑期避難所演習
(1)大阪府八尾市
2024(令和6)年7月下旬、大阪府八尾市の指定避難所の小学校体育館で、1泊2日の酷暑期避難所演習が実施されました。
松本孝朗氏は、演習時の研修会講師として講演し、また演習では車中泊をしました。
松本氏は、車中泊のときに車の後ろのハッチを全開放して寝たところ、風が止まり寝苦しかった時間帯と、南風が流れて涼しく感じた時間帯とがあったと報告されました。
避難生活では、風の流れ、夏には南風を考えて、避難所の窓や扉の開口部をつくるのがポイントになるでしょう。
この演習に、私も参加しました。
私は、体育館への避難は熱中症リスクが高く、夜間には屋外の車中泊やテント泊が選択肢になると感じたのです。
(2)青森県の弘前大学
2025(令和7)年8月中旬、弘前大学の体育館で、1泊2日の酷暑期避難所演習が開催されました。
この演習に、私も参加しました。
体育館内で、扉の開放、スポットクーラーや扇風機などが使われるなか、午後の室温が31.3℃になりました。
じっとしていても、背中に汗がにじみます。
体育館2階のスペースを歩くと、直射日光があたる屋根と接する天井から輻射熱を顔に感じます。
1階と比べて、温度が1℃以上高くなっていました。
その半面、外気温の低下とともに、午前1時すぎ、室温が23.7℃まで下がり、扇風機の風があたると、肌寒さを感じました。
冷房が止められ、扉が閉まりました。
昼夜の温度差に、体調を崩しそうになりました。
2 暑さ指数(WBGT)
湿球黒球温度とも呼ばれ、熱中症を予防することを目的に1954年にアメリカで提案された指標です。
測定には、黒い球の中に温度計が入っている湿球黒球温度計を使います。
熱中症計ともいわれています。
測定単位は、気温と同じ摂氏度(℃)で示されます。
気温との混同を避けるため、数値のみで表現されることがあります。
熱中症計について、JIS規格(2017)クラス2(±2℃)の表記がされているものがあります。
日本生気象学会「日常生活に関する指針」で、暑さ指数がレベル分けされています。
・危険(31以上)レベル
高齢者が安静状態でも熱中症になる危険性が高くなります。
涼しい室内に移動することが必要です。
・厳重警戒(28以上31未満)レベル
外出時に炎天下を避けることが大切です。
室内の温度上昇に注意しましょう。
環境省の熱中症予防情報サイトでは、熱中症警戒アラート(WBGT 33℃以上)・暑さ指数等の配信サービスが案内されています。
暑さ指数の算出式は、屋外と屋内で違います。
(屋外)
WBGT=0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度
(屋内)
WBGT=0.7×湿球温度+0.3×黒球温度
3 熱中症の症状と対処
熱中症とは、暑さにより起こる病気の総称です。
熱失神、熱けいれん、熱疲労、熱射病の四つに分類されます。
①熱失神
炎天下にいたり運動をしたりしたとき、めまいや失神などの症状が出ます。
横になることで、血液が体をまわり回復へ向かいます。
②熱けいれん
大量に汗をかき水だけを補給したときに、足などがつる症状です。
塩分を補給することで回復へ向かいます。
(参考)飲み物等の塩分濃度
・一般的なスポーツドリンク :0.1 %
・製薬会社のスポーツドリンク:0.12%
・経口補水液 :0.3 %
・生理食塩水(点滴) :0.9 %
夏季に激しい運動をするとき、水分補給に経口補水液が推奨されています。
夏季以外の軽い運動では、水分補給に水、麦茶などでいいといわれています。
③熱疲労
運動中の脱水で、めまい、頭痛、吐き気などの症状が出ます。
運動の休止、水分・塩分の補給、体を冷やすことで回復へ向かいます。
④熱射病
命の危険があるのが熱射病です。
体温が40℃以上になり、脳が熱くなることで脳機能障害が起き、意識レベルが落ちて、体温調整ができなくなります。
意識障害、応答が鈍い、言動がおかしいという状態になります。
多臓器不全の可能性があります。
救急車を要請して、速やかに体に水をかけるなど冷却措置が必要になります。
(対応例)
・水槽などで氷水に全身をつける。
・ホースで水をかけ、扇風機などで風を送る。窒息の可能性があるので、顔には水をかけない。
・冷房のある部屋で、裸にして、全身に濡れたタオルを乗せる。タオルは、濡らしたタオルと変えていく。扇風機をかける。
脇の下に冷たいものを入れるだけでは十分ではありません。
※救急車を呼ぶことが大切です。
4 症例
・熱疲労:40代男性、炎天下のゴルフで頭痛・吐き気
・熱射病:40代男性、炎天下のマラソンで意識昏迷・全身痙攣
・熱射病:10代男性、炎天下のアメフト練習で強直性痙攣・体温42℃以上
・熱射病:80代男性、梅雨明けの急激な暑さで、室内で意識混濁・体温39℃台・脱水
5 酷暑期の避難所の熱中症対策
①エアコンの教室を用意する
②水シャワーで体を冷やす
体温を下げるのは、水シャワーが効果的です。
③スポーツドリンクの備蓄
汗をかいたときの塩分補給のために、スポーツドリンクの備蓄が大切です。
④発災48時間以内にTKB整備
トイレ、キッチン、ベッドの環境整備が重要です。
(注意)
酷暑期、炎天下で復旧作業をするのは危険です。
熱中症対策は難しいとされています。
日中の避難所は、高齢者にとって危険と考えられます。
酷暑期、エアコンと電気なしには、熱中症対策は困難と考えられています。
夜も暑さで寝苦しく、睡眠不足になると、よけいに体調を崩しやすくなります。
6 熱中症対策の資料
松本孝朗氏が制作に関わった資料は、次のとおりです。
①スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック
日本スポーツ協会
※日本スポーツ協会のホームページで、デジタル版(PDF)がダウンロードできます。
②日常生活における熱中症予防
日本生気象学会
※日本生気象学会のホームページで、熱中症予防研究委員会のページから、デジタル版(PDF)がダウンロードできます。
③熱中症環境保健マニュアル
環境省
※環境省のホームページで、熱中症予防情報サイトの普及啓発資料のページから、デジタル版(PDF)がダウンロードできます。
7 環監の視点
電気が止まったときの熱中症対策として、自家用車やバスなどを使い、車内のエアコンで体を冷やす方法が考えられます。
平時から、ガソリンや軽油など燃料の確保、EV車の充電などを考える必要があります。
熱中症対策として、海上の客船などを使う方法も選択肢のひとつでしょう。
電気を局所的に供給できる電源車の活用も選択肢のひとつになるでしょう。
【災害時の衛生対策のご相談】
ご相談、ご質問などありましたら、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームにご記入ください。
災害時の衛生対策、避難所・避難生活の衛生対策の講師ご依頼につきまして、お気軽にお問い合わせください
『災害時・避難所の衛生対策のてびき』ご購入をお考えのかたは、こちらから注文ができます。
【ご案内】
【2025(令和7)年度講座】
2025(令和7)年度のオフィス環監未来塾の講座一覧表をご覧いただけます。
・環監業務の悩み、課題がありましたら、ご相談をお受けしています。
・課題の解決につながる講座をご用意しています。
・保健師の皆様への研修のご相談、避難所の衛生対策活動等のご相談をお受けしています。
月に数回、環監のための、レジオネラ症対策、防災、仕事術、講座情報など、最新情報をメールで真っ先にお届けします。ご希望される場合、こちらにご記入ください。
【活動実績】
(本・図書・出版物)
・2025年、介護保険専門紙『シルバー新報』(環境新聞社)で「介護現場のBCP 災害時の知識」を連載中です。
・2025年、月刊誌『クリンネス』(イカリホールディングス株式会社)で「衛生視点で感染症・災害時のBCPを考える」を連載中です。
・2022年、本『災害時・避難所の衛生対策のてびき』根本昌宏監修(一般財団法人日本環境衛生センター)を出版しました。
・2021年、専門誌『生活と環境』(一般財団法人日本環境衛生センター)で「災害時の居住環境 ~保健所・環境衛生監視員の視点から~」を連載しました。
・2020年、『災害時の保健活動推進マニュアル』(日本公衆衛生協会・全国保健師長会、令和2年3月)で「生活環境衛生対策」(避難所の環境衛生管理アセスメント)を分担執筆しました。
(活動)
被災地の地元自治体に協力して避難所の衛生対策活動・調査をしました。
・2024年、能登半島地震(石川県、珠洲市、七尾市)
奥能登豪雨(石川県、珠洲市)
・2019年、令和元年台風19号(長野市、いわき市)
・2018年、西日本豪雨(倉敷市)
・2016年、熊本地震(熊本市)
・2011年、東日本大震災(気仙沼市)
(調査活動)
・1995年、阪神・淡路大震災
(講師)
・2025年、神奈川県公衆衛生協会平塚支部講演会「災害時の公衆衛生活動、~災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策、保健所・環境衛生監視員の視点から~」
・2025年、豊田市役所研修「災害時の避難所等における衛生対策に関する研修」
・2025年、豊橋市保健所研修会「災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策 ~避難生活で健康を守るポイント~」
・2025年、日本災害食学会・災害食専門員研修会「災害時の水の安全・衛生」
・2024年、神奈川県公衆衛生学会「シンポジウム・避難所における健康危機管理」
・2024年、宮城県気仙沼圏域研修「災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策 ~保健所・環境衛生監視員の視点から~」
・2024年、宮城県登米地域災害対応研修「災害時における環境衛生対策」
・2024年、愛知県看護協会・研修会「災害時の生活環境衛生対策の課題と実際」
・2024年、福井県嶺南地域保健・福祉・環境関係職員研修「災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策 ~保健所・環境衛生監視員の視点から~」
・2024年、鳥取県市町村保健師協議会研修会「災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策 ~保健所・環境衛生監視員の視点から~」
・2024年、全国保健師長会、能登半島地震関連・緊急オンライン研修会「地震断水時の避難所・避難生活の衛生対策」
・2023年、令和5年度 兵庫県・北播丹波ブロック市町保健師協議会・研修会「災害時の避難所の衛生、感染症対策」
・2023年、第54回 沖縄県衛生監視員研究発表会及び研修会・特別講演「災害時・避難所の衛生対策について」
・2022年、国立保健医療科学院、令和4年度 住まいと健康研修「災害時の公衆衛生活動」(オンライン)
・2022年、東京都特別区職員研修所、令和4年度専門研修「地域保健」(主に保健師対象)「災害時の避難所の衛生・感染症対策、保健所・環境衛生監視員の視点から」
(学会)
・2025年、第30回日本災害医学会総会・学術集会「サーモグラフィ画像を活用した避難所の環境衛生管理」
・2025年、第52回建築物環境衛生管理全国大会「能登半島地震被災地の公衆衛生活動者を支援するためのIT活用の成果」
・2023年、日本防菌防黴学会・第50回年次大会「令和4年台風第15号による大雨被災地の泥から検出されたレジオネラ属菌について」
・2021年、日本防菌防黴学会・第48回年次大会(オンライン開催)「令和元年東日本台風(台風19号)被災地の泥から検出されたレジオネラ属菌について」
・2021年、第48回建築物環境衛生管理全国大会(オンライン開催)「令和元年東日本台風(台風19号)被災地の避難所の施設・空気環境の実態」奨励賞受賞
・2020年、第79回日本公衆衛生学会総会(オンライン開催) 「令和元年台風19号被災地の避難所における空気環境等の実態」
・2012年、第39回建築物環境衛生管理全国大会「東日本大震災被災地の避難所の施設・空気環境の実態」最優秀賞受賞