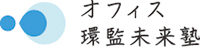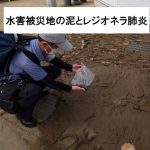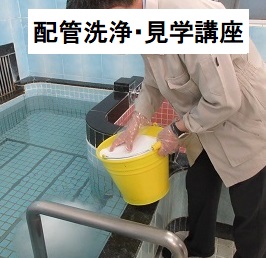【保健師・環監向け】災害時の衛生・し尿ごみの臭い
【災害時の衛生・し尿ごみの臭い】
1 し尿の臭い成分
2 臭い成分とガス
3 し尿ごみの保管場所
4 環監の視点(比重から考える)

元文京区文京保健所・環境衛生監視員(環監)で、『災害時・避難所の衛生対策のてびき』著(根本昌宏監修、一般財団法人日本環境衛生センター)、避難所衛生対策・レジオネラ症対策の研修講師をしている「オフィス環監未来塾」中臣昌広です。
2025(令和7)年2月上旬に、都内で、特別区第4ブロック(中野区、杉並区、板橋区、練馬区、豊島区)主催の「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づくビル衛生管理講習会の講師をつとめました。
テーマ「建築物衛生と災害時衛生との接点、保健所・環境衛生監視員の視点から」をお話ししました。
会場に、ビル施設の関係者約200人のかたが参加されました。
簡単なワークで、災害時にライフラインが止まったとき、ビルで、し尿ごみをどこに置いたらいいのかを考えていただきました。
建物内がいいのか、敷地の屋外がいいのか、どちらでしょうか。
考える基準として、臭いの影響をあげたかたがいました。
し尿ごみの問題は、衛生面とともに、臭いと言っていいでしょう。
し尿ごみの臭いは、災害時の避難所・避難生活の衛生対策を考えるうえでも有用ですので、考えてみたいと思います。
下記の記述は、災害廃棄物分野・専門家の元一般財団法人日本環境衛生センター・森田昭氏のご意見を参考にしました。
1 し尿の臭い成分
(1)臭い成分
し尿の臭いは、いろいろな成分が混ざった複合臭です。
なかでも、悪臭成分は、主に次の4種類といわれています。
・メチルメルカプタン(腐ったタマネギのような臭い)
・硫化水素(腐った卵のような臭い)
・硫化メチル(腐ったキャベツのような臭い)
・二硫化メチル(腐ったキャベツのような臭い)
また、尿成分は、アンモニアです。
実際に人が感じる臭いは、複合臭です。
ちなみに、悪臭防止法では、人の嗅覚で感じる官能試験法が使われています。
(2)臭気指数
環境省の資料「においの評価」によると、においの程度を数値化した臭気指数があります。
具体的には、もとのにおいを人間の嗅覚で感じられなくなるまで無臭空気で薄めたたおきの希釈倍数(臭気濃度)を求め、その常用対数に10を乗じた値となっています。
例として、悪臭の規制について、住宅地の目安のひとつの臭気指数10は、梅の香り程度といわれています。
し尿ごみは、臭気指数でいえば高い値になるでしょう。
臭気指数から見ると、成分ごとに濃度と臭いの強さが異なるのがわかります。
要は、濃度が低くても、強い臭いを発する物質があるのです。
上記のメチルメルカプタンや、ノルマル酪酸(汗くさい臭い)、ノルマル吉草酸(蒸れた靴下の臭い)が当たります。
(3)ビニール袋内で臭いが強くなる
通常、携帯トイレや簡易トイレのし尿ごみは、ビニール袋に入って保管がされます。
ビニール袋が破れると、周囲に強い臭いが拡散します。
密閉されたビニール袋内では、し尿中の有機物が嫌気分解されて臭気を強める可能性があるからです。
嫌気分解とは、空気中の酸素が少ない状態での微生物による分解のことです。
熊本地震のとき、し尿ごみの収集が滞り、ごみ保管場所の周囲で悪臭問題が起きました。
東日本大震災の避難所のなかには、穴を掘って袋を地中に保管し、シートで覆った例があります。
2 臭い成分とガス
(1)空気より軽いのか
臭い成分が空気より軽いか重たいかをみるのは、比重の数値があります。
空気を1として、空気より軽いのは1より小さい数値です。
空気より重たいのは1より大きな数値です。
森田氏の資料によると、し尿ごみの主な臭い4物質は、次のとおりです。
メチルメルカプタン:0.896
硫化水素 :ー
硫化メチル :0.845
二硫化メチル :1.057
し尿は、空気より軽い成分が比較的多いと考えられています。
(2)ガスのリスク
し尿ごみは、微生物による分解がされます。
微生物は、空気中の酸素を必要とする好気性微生物と、酸素の必要がない嫌気性微生物の二つの種類があります。
空気にふれた、し尿ごみは、好気性微生物が酸素を消費するので、狭い密閉された空間に置くと、室内の酸素が欠乏する可能性があります。
密閉されたビニール袋内のし尿ごみは、嫌気性微生物により、可燃性のメタンガスや有毒な硫化水素ガスなどが発生することがあります。
ちなみに、メタンガスは、無色、無臭で、空気より軽い物質です。
たとえば、ビル地下のコンクリート壁のごみ置き場室に、し尿ごみを置いたとしましょう。
酸素の不足や、可燃性ガス、有毒ガスの発生のリスクが出てくるかもしれません。
先日、コンクリート製の下水道管の劣化について、管内で汚水から硫化水素ガスが放出されると、コンクリート付着の細菌の働きにより酸化されて、硫化水素が硫酸に変化し、コンクリートの腐食につながる可能性があると聞きました。
コンクリート壁のごみ置き場室に、し尿ごみを置いて、硫化水素ガスが放出されたとき、コンクリートの腐食の恐れがないか気になりました。
3 し尿ごみの保管場所
(1)密閉空間の室内置きを避ける
建物内の密閉された空間に置くのは、大きなリスクがあります。
前記のように、酸素不足や、有毒ガス・可燃性ガスの発生の可能性があり、命・健康を守るために、し尿ごみの密閉空間の室内置きを避けましょう。
(2)ビルは屋上が候補
し尿ごみの、臭いの問題や、微生物の酸素消費、有毒ガス・可燃性ガスの発生を考えると、し尿ごみの保管場所は、ビル内であれば、屋上が候補になります。
日よけ、雨よけに、ブルーシート類で覆います。
ただし、空気より重い臭い成分による近隣への臭気の拡散、上階への持ち運びの労力、収集時の階下への運搬の労力、運搬時の飛散など、デメリットもあるでしょう。
自治体によっては、し尿ごみ等の生活ごみについて、マンションでの災害時ごみ集積場所の確保を推奨しています。
(3)屋外保管が基本
避難所の小中学校を考えると、屋外保管が基本的な考えになると思います。
理想的には、日常に、災害時のごみ集積場所に転用できる、敷地内・校庭等に小屋があればいいでしょう。
別ページで、し尿ごみ(排泄物ごみ)の置き場所に詳しくふれています。
4 環監の視点(比重から考える)
私がし尿ごみの臭いを考えたきっかけは、メタンガスの誤理解からでした。
排泄物の臭い成分は、空気より軽いメタンガスだと思いこんでいました。
前記講習会参加者のご指摘のおかげで、メタンガスが無色無臭だと気づき、臭い成分を調べ直すことにしました。
私が着目したのは、成分の比重です。
空気より軽い成分が多ければ、し尿の臭いが階下から階上へ行くことになります。
建物内に限定して考えたとき、臭いの影響を抑えるには、屋上に保管するのがいいことがわかりました。
室内に置くリスクが大きいこともわかりました。
災害時の避難所では、し尿ごみの臭いや発生するガスを考慮しながら、季節の風向き、ごみ収集車の出入りなどを踏まえて、限られた選択肢のなかで、し尿ごみの保管場所をきめることが求められます。
災害時の衛生対策、避難所・避難生活の衛生対策のご質問、ご相談など、お気軽にお問い合わせください
災害時の衛生対策、避難所・避難生活の衛生対策の講師ご依頼につきまして、お気軽にお問い合わせください
『災害時・避難所の衛生対策のてびき』ご購入をお考えのかたは、こちらから注文ができます。
【ご案内】
【2024(令和6)年度講座】
2024(令和6)年度のオフィス環監未来塾の講座一覧表をご覧いただけます。
【2025(令和7)年度講座】
2025(令和7)年度のオフィス環監未来塾の講座一覧表をご覧いただけます。
・環監業務の悩み、課題がありましたら、ご相談をお受けしています。
・課題の解決につながる講座をご用意しています。
・保健師の皆様への研修のご相談、避難所の衛生対策活動等のご相談をお受けしています。
月に数回、環監のための、レジオネラ症対策、防災、仕事術、講座情報など、最新情報をメールで真っ先にお届けします。ご希望される場合、こちらにご記入ください。
【実績】
(書籍)
・2022年、『災害時・避難所の衛生対策のてびき』根本昌宏監修(一般財団法人日本環境衛生センター)を出版しました。
・2020年、全国保健師長会・作成『災害時の保健活動推進マニュアル』の生活環境衛生対策の分担執筆をしました。
(活動)
・被災地の地元自治体に協力して避難所の衛生対策活動・調査をしました。
2011年 東日本大震災、気仙沼市
2016年 熊本地震、熊本市
2018年 西日本豪雨、倉敷市
2019年 令和元年台風19号、長野市、いわき市
2024年 能登半島地震、七尾市、珠洲市
(講師)
・2024年、鳥取県市町村保健師協議会研修会「災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策 ~保健所・環境衛生監視員の視点から~」の講師をつとめました。
・2024年、全国保健師長会、能登半島地震関連・緊急オンライン研修会「地震断水時の避難所・避難生活の衛生対策」の講師をつとめました。
・2023年、令和5年度 兵庫県・北播丹波ブロック市町保健師協議会・研修会で、「災害時の避難所の衛生、感染症対策」の講師をつとめました。
・2023年、第54回 沖縄県衛生監視員研究発表会及び研修会で、特別講演「災害時・避難所の衛生対策について」の講師をつとめました。
・2022年、国立保健医療科学院、令和4年度 住まいと健康研修で「災害時の公衆衛生活動」(オンライン)の講師をつとめました。
・2022年、東京都特別区職員研修所、令和4年度専門研修「地域保健」(主に保健師対象)で、「災害時の避難所の衛生・感染症対策、保健所・環境衛生監視員の視点から」の講師をつとめました。