【大規模火災】避難所の空気環境とインフルエンザ対策・その1
【避難所の空気環境とインフルエンザ対策】その1
1 避難所の構造から考える
2 温度・湿度の測定
3 冷え対策と加湿
4 環監の視点(空気環境の実態を把握する)
上の画像をクリックすると、pdfが開きます。

(2011年、東日本大震災被災地で)
元文京区文京保健所・環境衛生監視員で、『災害時・避難所の衛生対策のてびき』著(根本昌宏監修、一般財団法人日本環境衛生センター)、避難所の衛生対策・レジオネラ症対策の研修講師をしている「オフィス環監未来塾」中臣昌広です。
2025(令和7)年11月18日(火)に、大分市佐賀関で大規模な火災が発生しました。
火災地域の皆様へお見舞い申しあげます。
令和7年11月25日付大分県災害警戒本部の資料によると、25日12時時点で、佐賀関市民センター内佐賀関公民館に、71世帯、110名のかたが避難しています。
11月25日(火)昼のテレビニュースを見て理解したのは、24日時点で、避難所でインフルエンザ患者14人が確認されたということです。
別のニュース映像では、予防投与として希望者にタミフルを配布しているのを見ました。
次のとおり、【大規模火災】避難所の空気環境とインフルエンザ対策について、これまでの被災地での避難所衛生対策活動の経験を基に、保健所・環境衛生監視員の視点でまとめています。
その1では、温度・湿度の視点から、その2では、飛沫感染対策の視点から考えていきます。
今回は、その1を考えます。
ご活用ください。
別ページに、【大規模火災】避難所の空気環境とインフルエンザ対策・その2があります。
別ページに、【冬季の避難所】空気環境とインフルエンザ対策・加湿があります。
加湿の方法、加湿器の衛生管理のポイントなどを紹介しています。
別ページに、【冬季の避難所】空気環境とインフルエンザ対策・換気について、詳しく書いています。
1 避難所の構造から考える
(1)小体育館の空気環境
①床面の冷え
まず、避難所の避難スペースについて、温度・湿度を測定して、実態を把握するのが大切だと思います。
大分市のホームページから、佐賀関公民館の平面図と、集会室、研修室、和室などの写真を見ることができました。
集会室は、卓球やバドミントンなどができる小体育館に見えます。
天井の高さは、5m以上あるように思えます。
天井には照明のほか、円形の穴が等間隔に並んでいて、空調の吹き出し口に見えます。
和室の天井には、冷暖房機が埋め込まれています。
集会室は、研修室や和室と比べて、天井が高く、空調で暖房しても上下温度差が生じて、床付近の温度が低くなり、床面からの冷えを感じやすくなるかもしれません。
集会室の入り口は、1階フロアにあり、玄関や出入り口が開いたとき、外の冷気が集会室の床面へ移行してしまう可能性があると感じました。
発災当初の映像では、床にマットを敷いて、その上に寝具を置いて寝ている様子がわかりました。
寝ていて、冷えを感じていたかもしれません。
②空気の乾燥
体育館では、運動による発汗があり、水蒸気が空気中に多くなって湿度が上がることを想定して、空調設備に加湿機能をつけないことがあります。
実際に、2019年の台風19号被災地の長野市で、避難所となった体育館で、空調に加湿装置がなく、空気の乾燥が問題になりました。
今回、避難スペースとなった集会室の小体育館で、空調に加湿機能がないのではないかと考えました。
③インフルエンザ流行の原因のひとつ
空気が乾燥すると、気道粘膜の防御機能が低下して、インフルエンザにかかりやすくなるといわれています。
原因のひとつを推測してみました。
避難に伴う身体的・精神的な疲れにより免疫力が低下したなかで、体の冷えや空気の乾燥が原因のひとつになって、避難所内で感染が広がった可能性があると考えました。
災害時の衛生対策、避難所・避難生活の衛生対策のご質問、ご相談など、お気軽にお問い合わせください。
災害時の衛生対策、避難所・避難生活の衛生対策の講師ご依頼につきまして、お気軽にお問い合わせください。
2 温度・湿度の測定
避難所の平面図を用意し、測定箇所をできるだけ細分化して等間隔でプロットし、温度と湿度を測定します。
(1)空気環境の基準
二つの基準があります。
①建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)
・温度 18~28 ℃
・湿度 40~70 %
・二酸化炭素濃度 1,000 ppm 以下
・一酸化炭素濃度 6 ppm 以下
・浮遊粉じん量 0.15 mg/L 以下
②学校環境衛生基準
・温度 18~28 ℃ 望ましい
・湿度 30~80 % 望ましい
・二酸化炭素濃度 1,500 ppm 以下 望ましい
・一酸化炭素濃度 6 ppm 以下
・浮遊粉じん量 0.10 mg/L 以下
建築物衛生法の対象の、床面積3,000m3の事務所・店舗などのビルは、空調設備・換気設備をもつ施設がほとんどです。
基本的に、機械的な調整によって、空気環境が保たれています。
一方、学校環境衛生基準は、窓開けの自然換気による教室も対象になっています。
したがって、建築物衛生法と比べて、幅が広い基準値があります。
※避難所では、厳密な空気環境基準はありません。
(2)温度・湿度の目安
冬の暖房時の室温の目安は、18~22℃です。
冬の暖房時の室内湿度の目安は、40~50%です。
温度・湿度は、東京都の「健康・快適居住環境の指針」を参考にしています。
(3)測定方法
床面から高さ75~150cmで測定します。
椅子に腰かけたときの顔の高さくらいになります。
(4)床上10cmでの測定
床からの冷えを確認するため、床上10cmでも測定します。
このとき、床上75~150cmの測定値と比較して、上下の温度差が1~2℃を超える状況では、空気がかくはんされていないと考えられます。
(5)赤外線放射温度計
非接触型体温計が、この原理を利用しています。
メーカーにより、切り替えスイッチで、物体の表面温度を測ることができます。
床面の表面温度を測り、冷える状況があるかを確認することができます。
15℃以下:寒いと感じる温度です。
10℃以下:冷蔵庫の中にいるくらいの温度です。
(6)温度・湿度計の常設
温度・湿度計を壁につけて、確認するとよいでしょう。
高さ 75~150 cmの位置です。
最低、1日2回、午前10時と午後2時に数値を確認して、記録をします。
夜の状況として、午後8時頃に測定してもいいでしょう。
3 冷え対策と加湿
(1)段ボールベッドと段ボールパーティション
今回、避難所への段ボールベッドの導入の話を聞きました。
床上35cmの段ボールベッドの使用は、床面からの冷えを抑えてくれます。
床面の埃の吸い込みを抑えることもできます。
段ボールの素材は、空気層をもっていて、人からの放熱により温まり、保温効果を高めます。
寒さを感じるときは、体と段ボールパーティションとの距離が近いほうが温まりやすくなります。
床面に断熱材を敷いて、保温性を高めてもいいと思います。
(2)防災テントの改善
防災テントは、素材が薄いため、能登半島地震被災地の避難所では「寒かった」との声を聞きました。
防災テントの内側に段ボールの内壁をつくることで、保温性が高まります。
寝るときには、天井に覆いをかぶせると、防災テント内の保温性が高まります。
(3)室内の加湿
室内では、マスク着用、湿度アップがインフルエンザ予防に大切です。
冬の室内の湿度の目安は、40~50%です。
湿度が低めのときは加湿器を有効活用するといいでしょう。
加湿器は、加熱式、超音波式、気化式の3つのタイプと、それぞれを組み合わせたハイブリッド型があります。
小学校の教室や公民館の部屋などの天井が低く小さい空間では、濡れタオルを干すことや卓上型加湿器の使用が湿度アップに有効です。
石油ストーブに乗せたやかんの湯気は、室内の加湿に有効です。
小体育館での使用を考えると、やかんと同じ原理の加熱式の加湿器がおすすめです。
沸騰した蒸気が空気中に舞い、蒸気そのものは衛生的だからです。
湿度とともに温度の上昇もあるので、より暖かさを感じやすいと思います。
ただし、吹き出し口が高温になりますので、やけどに注意する必要があります。
手を近づけないようにしましょう。
加熱式は、ほかのタイプの加湿器と比べて電気を使うので、小体育館の電気容量が足りない場合、ほかのタイプの気化式、超音波式を使ってもいいでしょう。
この場合、毎日、水道水を交換する。週に1回程度、水のタンク等の清掃・消毒をする衛生管理が重要です。
別の方法で、過去の被災地の避難所では、ポリバケツに水を入れ、その中に筒状にした新聞紙10本の下側を漬けて、簡易加湿器をつくっていました。
水の毛細管現象と、水分の気化とを利用した加湿方法です。

(2019年、台風19号被災地の長野市の避難所で)
加湿器は、いずれのタイプも、毎日の水道水の入れ換えと定期的な水容器の清掃が必要になります。
カビや細菌類の発生を抑えるため、消毒の塩素を含む水道水を使用するのがポイントです。
別ページに、加湿器の仕組みや衛生管理の方法を詳細に説明しています。
4 環監の視点(空気環境の実態を把握する)
まず、空気環境の測定をして、測定値から評価をすることが必要だと思います。
そのうえで、冷え対策と加湿に着目して、具体的な改善策を実行してみる手順になると考えます。
空気環境は、体育館のように広い空間で天井が高く床が冷えやすい場所より、天井が低く比較的ちいさな空間のほうが、温度や湿度の管理がしやすいと考えられます。
私の過去の避難所衛生対策活動の経験と、保健所・環境衛生監視員の視点から、11月の朝夕の冷えがある時期には、避難所の避難スペースとして、公民館では研修室や和室の小さな空間のほうが向いていると感じます。
災害時の衛生対策、避難所・避難生活の衛生対策のご質問、ご相談など、お気軽にお問い合わせください
災害時の衛生対策、避難所・避難生活の衛生対策の講師ご依頼につきまして、お気軽にお問い合わせください
『災害時・避難所の衛生対策のてびき』ご購入をお考えのかたは、こちらから注文ができます。
【ご案内】
【2025(令和7)年度講座】
2025(令和7)年度のオフィス環監未来塾の研修講座の写真入り詳細をご覧いただけます。
【2026(令和8)年度講座】
2026(令和8)年度のオフィス環監未来塾の研修講座の写真入り詳細をご覧いただけます。
・環監業務の悩み、課題がありましたら、ご相談をお受けしています。
・課題の解決につながる講座をご用意しています。
・保健師の皆様への研修のご相談、避難所の衛生対策活動等のご相談をお受けしています。
月に数回、環監のための、レジオネラ症対策、防災、仕事術、講座情報など、最新情報をメールで真っ先にお届けします。ご希望される場合、こちらにご記入ください。
【活動実績】
(本・図書・出版物)
・2025年、介護保険専門紙『シルバー新報』(環境新聞社)で「介護現場のBCP 災害時の知識」を連載中です。
・2025年、月刊誌『クリンネス』(イカリホールディングス株式会社)で「衛生視点で感染症・災害時のBCPを考える」を連載中です。
・2022年、本『災害時・避難所の衛生対策のてびき』根本昌宏監修(一般財団法人日本環境衛生センター)を出版しました。
・2021年、専門誌『生活と環境』(一般財団法人日本環境衛生センター)で「災害時の居住環境 ~保健所・環境衛生監視員の視点から~」を連載しました。
・2020年、『災害時の保健活動推進マニュアル』(日本公衆衛生協会・全国保健師長会、令和2年3月)で「生活環境衛生対策」(避難所の環境衛生管理アセスメント)を分担執筆しました。
(活動)
被災地の地元自治体に協力して避難所の衛生対策活動・調査をしました。
・2024年、能登半島地震(石川県、珠洲市、七尾市)
奥能登豪雨(石川県、珠洲市)
・2019年、令和元年台風19号(長野市、いわき市)
・2018年、西日本豪雨(倉敷市)
・2016年、熊本地震(熊本市)
・2011年、東日本大震災(気仙沼市)
(調査活動)
・1995年、阪神・淡路大震災
(講師)
・2025年、神奈川県公衆衛生協会平塚支部講演会「災害時の公衆衛生活動、~災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策、保健所・環境衛生監視員の視点から~」
・2025年、豊田市役所研修「災害時の避難所等における衛生対策に関する研修」
・2025年、豊橋市保健所研修会「災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策 ~避難生活で健康を守るポイント~」
・2025年、日本災害食学会・災害食専門員研修会「災害時の水の安全・衛生」
・2024年、神奈川県公衆衛生学会「シンポジウム・避難所における健康危機管理」
・2024年、宮城県気仙沼圏域研修「災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策 ~保健所・環境衛生監視員の視点から~」
・2024年、宮城県登米地域災害対応研修「災害時における環境衛生対策」
・2024年、愛知県看護協会・研修会「災害時の生活環境衛生対策の課題と実際」
・2024年、福井県嶺南地域保健・福祉・環境関係職員研修「災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策 ~保健所・環境衛生監視員の視点から~」
・2024年、鳥取県市町村保健師協議会研修会「災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策 ~保健所・環境衛生監視員の視点から~」
・2024年、全国保健師長会、能登半島地震関連・緊急オンライン研修会「地震断水時の避難所・避難生活の衛生対策」
・2023年、令和5年度 兵庫県・北播丹波ブロック市町保健師協議会・研修会「災害時の避難所の衛生、感染症対策」
・2023年、第54回 沖縄県衛生監視員研究発表会及び研修会・特別講演「災害時・避難所の衛生対策について」
・2022年、国立保健医療科学院、令和4年度 住まいと健康研修「災害時の公衆衛生活動」(オンライン)
・2022年、東京都特別区職員研修所、令和4年度専門研修「地域保健」(主に保健師対象)「災害時の避難所の衛生・感染症対策、保健所・環境衛生監視員の視点から」
(学会)
・2025年、第30回日本災害医学会総会・学術集会「サーモグラフィ画像を活用した避難所の環境衛生管理」
・2025年、第52回建築物環境衛生管理全国大会「能登半島地震被災地の公衆衛生活動者を支援するためのIT活用の成果」
・2023年、日本防菌防黴学会・第50回年次大会「令和4年台風第15号による大雨被災地の泥から検出されたレジオネラ属菌について」
・2021年、日本防菌防黴学会・第48回年次大会(オンライン開催)「令和元年東日本台風(台風19号)被災地の泥から検出されたレジオネラ属菌について」
・2021年、第48回建築物環境衛生管理全国大会(オンライン開催)「令和元年東日本台風(台風19号)被災地の避難所の施設・空気環境の実態」奨励賞受賞
・2020年、第79回日本公衆衛生学会総会(オンライン開催) 「令和元年台風19号被災地の避難所における空気環境等の実態」
・2012年、第39回建築物環境衛生管理全国大会「東日本大震災被災地の避難所の施設・空気環境の実態」最優秀賞受賞
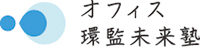
_page-0001-225x300.jpg)




-150x150.jpg)

