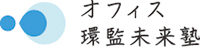【環監・保健師向け】レジオネラ・配管の高濃度塩素消毒の効果2
【配管の高濃度塩素消毒の効果2】
1 塩素剤による殺菌作用
2 高濃度塩素消毒の効果
3 次亜塩素酸ナトリウムによる殺菌原理
4 ATP値と次亜塩素酸ナトリウムの関係
5 環監の視点(原理を知る)
6 研修講座のご案内

こんにちは。元文京区文京保健所・環境衛生監視員で、『レジオネラ症対策のてびき』著(倉文明監修、一般財団法人日本環境衛生センター)、レジオネラ症対策・避難所衛生対策の研修講師をしている「オフィス環監未来塾」中臣昌広です。
2025(令和7)年9月下旬、三重県賢島で開催された「日本防菌防黴学会 第52回年次大会」に出席して、ポスター発表をしました。
タイトルは、「令和6年能登半島地震の津波被災地の泥及び奥能登豪雨被災地の泥から検出されたレジオネラ属菌について」です。
この詳細は、後日、別のページでご案内します。
今回は、同会場のポスター発表でお話を聞いた「次亜塩素酸ナトリウムによるバイオフィルム中のレジオネラ除菌効果」(アクアス(株)・つくば総研 小野寺順子氏、伊藤雅代氏、縣邦雄氏)から、私が理解した内容を基に、塩素剤による殺菌作用を考えてみます。
1 塩素剤による殺菌作用
前記の小野寺順子氏の発表は、公衆浴場等の循環処理の配管内のバイオフィルムを、モデル的につくり、殺菌剤がレジオネラ属菌に除菌効果をもたらすかを確かめたものです。
殺菌剤として、次亜塩素酸ナトリウム、過酸化水素、過炭酸ナトリウム、モノクロラミンが用いられました。
用いられた殺菌剤
①次亜塩素酸ナトリウム 50 mg/L
②次亜塩素酸ナトリウム 0.1 %
③次亜塩素酸ナトリウム 0.2 %
④過酸化水素 1 %
⑤過酸化水素 2 %
⑥過炭酸ナトリウム 0.5 %
⑦モノクロラミン 50 mg/L
配管内に、各殺菌剤を1時間浸け置きしたあと、レジオネラ属菌の培養法・遺伝子(定量PCR)検査がおこなわれました。
比較に、残留塩素を除去した水道水も同様に試験されました。
バイオフィルム中のレジオネラ属菌については、用いられた殺菌剤すべてで、不検出になりました。
レジオネラの遺伝子分解を、定量PCR法からみると、次亜塩素酸ナトリウムが他の殺菌剤と比べて、遺伝子量が低くなっています。
殺菌剤①は、遺伝子量が99.99 %以上、減少しました。
②及び③は、遺伝子が不検出となりました。
殺菌剤⑦のモノクロラミンは、36 %の減少率でした。
殺菌剤④⑤⑥は、遺伝子の減少は認められませんでした。
2 高濃度塩素消毒の効果
上記の実験結果から、推測できる点を考えました。
(1)高濃度塩素消毒の効果
保健所から、公衆浴場等の循環配管について、週に1回程度の高濃度塩素消毒が指導・助言されています。
高濃度塩素消毒の濃度は、通常、5~10 mg/Lになります。
上記の実験では、その数値より高めの、次亜塩素酸ナトリウム 50 mg/Lで除菌効果があることがわかります。
配管の高濃度塩素消毒は、実験のように、途中でポンプを止めて、浸け置きしてもいいのではないかと思いました。
(2)薬剤による配管洗浄の工程
保健所から、公衆浴場等の循環配管について、年に1回以上、薬剤による配管洗浄が指導・助言されています。
過酸化水素や過炭酸ナトリウムを用いた配管洗浄では、薬剤による配管洗浄のあと、次亜塩素酸ナトリウムを使う殺菌工程を目にします。
別ページに、配管洗浄の工程の説明があります。
上記実験から、次亜塩素酸ナトリウムが、遺伝子量を減少させていることがわかりました。
したがって、この工程を入れることで、配管洗浄後の効果判定の迅速法水質検査で、レジオネラが陰性になるということになります。
なお、迅速法のPCR法やLAMP法は、死菌を含めた遺伝子量を測るものです。
薬剤による配管洗浄では、次亜塩素酸ナトリウムによる殺菌工程が欠かせないことがわかります。
レジオネラ症対策のご質問、ご相談など、お気軽にお問い合わせください
レジオネラ症対策の講師ご依頼につきまして、お気軽にお問い合わせください
3 次亜塩素酸ナトリウムによる殺菌原理
『保健環境論』村瀬誠著(京都廣川書店)には、次亜塩素酸ナトリウムと殺菌機構が説明されています。
私が理解した内容は、次のとおりです。
細菌は、外側が細胞壁に覆われています。
細胞壁は、イオンや低分子量の親水性分子を透過させます。
逆に、細胞膜の内側にある細胞質膜は、イオンや低分子量の親水性分子を通しません。
したがって、イオン化した次亜塩素酸イオン(⁻OCl)は、細胞の内側に入ることができません。
一方で、次亜塩素酸(HOCl)は、細胞の内側まで入ることができます。
細胞内に入ったHOClは、細胞質膜や細胞質のDNAやRNAなど有機物に酸化作用を与えます。
掲載図を見ると、HOClが細胞内のDNAにダメージを与えている様子がわかります。
つまり、遺伝子の構造が壊れてしまうのです。
浴槽水について、遺伝子検査のレジオネラ迅速法で陰性になる一例は、殺菌により遺伝子構造が壊れ、遺伝子量が減るためです。
ただし、レジオネラ属菌の量が多い場合、十分な次亜塩素酸ナトリウムの量や接触時間がないと、遺伝子構造が残存すると思われます。
過酸化水素や過炭酸ナトリウムなどの配管洗浄の工程で、次亜塩素酸ナトリウムによる殺菌を加えているのは、レジオネラ属菌の遺伝子構造を壊し、迅速法で陰性するための手段と言っていいかもしれません。
4 ATP値と次亜塩素酸ナトリウムの関係
2025(令和7)年10月に仙台で開催された第69回生活と環境全国大会の「全国環境衛生職員団体協議会 事例研究発表会」で、参考になる発表がありました。
発表演題は、次のとおりです。
「モノクロラミンを使用する入浴施設における簡便な維持管理指標 ATP検査の実効性の検証と有機物量との相関」
猪俣宏貴氏、添野恭子氏、藤井順子氏、岸岡美樹氏、毛利淳子氏(仙台市泉区保健福祉センター衛生課)
抄録原稿で、私が注目したのは、浴槽水 300 mL に次亜塩素酸ナトリウムを添加して、遊離残留塩素濃度が約1 mg/L のときの、経過時間とATP値のグラフです。
ATP値とは、生物由来の有機物を測定した値です。
単位は、RLU として表されます。
実験では、時間の経過とともに、当初約 150 RLU あったATP値が減っていき、1時間後に半減、翌日には、ほぼゼロになりました。
このことは、前記したように、次亜塩素酸ナトリウムが細菌の細胞などの有機物に作用して、有機物を分解したために、ATP値が下がったと考えられます。
5 環監の視点(原理を知る)
あらためて、次亜塩素酸ナトリウムが、どのようにレジオネラ属菌の遺伝子量を減らすのかを理解しました。
特に、前述したとおり、次亜塩素酸ナトリウムの殺菌原理を確認できたのは、環監にとって意味があります。
原理を知ることによって、自信をもって現場で衛生管理の指導・助言をすることができるからです。
知識を増やし、現場にのぞんでいきましょう。
レジオネラ症対策のご質問、ご相談など、お気軽にお問い合わせください
レジオネラ症対策の講師ご依頼につきまして、お気軽にお問い合わせください
【ご案内】
【2025(令和7)年度講座】
2025(令和7)年度のオフィス環監未来塾の研修講座の写真入り詳細をご覧いただけます。
【2026(令和8)年度講座】
2026(令和8)年度のオフィス環監未来塾の研修講座の写真入り詳細をご覧いただけます。
『レジオネラ症対策のてびき』の概要はこちらから確認できます。ご購入をお考えのかたも、こちらから注文ができます。
・環監業務の悩み、課題がありましたら、ご相談をお受けしています。
・課題の解決につながる講座をご用意しています。
・保健師の皆様への研修のご相談、避難所の衛生対策活動等のご相談をお受けしています。
月に数回、環監のための、レジオネラ症対策、防災、仕事術、講座情報など、最新情報をメールで真っ先にお届けします。ご希望される場合、こちらにご記入ください。
【活動実績】
(書籍・図書)
・2024年、専門誌『設備と管理』(オーム社)に「冷却塔の清掃方法とレジオネラ症 保健所・環境衛生監視員の視点から」を執筆しました。
・2023年、専門誌『設備と管理』(オーム社)に「老舗旅館の大浴場、湯の入れ換えが年2回 レジオネラ症対策を再考する」を執筆しました。
・2015年、専門誌『生活と環境』(一般財団法人日本環境衛生センター)に「公衆浴場・温泉・旅館業・スポーツ施設・介護保険施設のための 続・よくわかるレジオネラ症対策」を連載しました。
・2013年、『レジオネラ症対策のてびき』倉文明監修(一般財団法人日本環境衛生センター)を出版しました。
(活動)
・2024年、厚生労働科学研究費補助金(健康安全・危機管理対策総合研究事業)「公衆浴場の衛生管理の推進のための研究」の研究協力者として活動しました。
・2024年、厚生労働省のレジオネラ対策のページに掲載されている「入浴施設の衛生管理の手引き(令和4年5月13日)」改定検討の研究協力者として、元神奈川県衛生研究所・黒木俊郎先生らと共に活動しました。
・2022年、「入浴施設の衛生管理の手引き(令和4年5月13日)」の作成ワーキンググループのメンバーに、国立感染症研究所・倉文明先生らと共になりました。
・2017年、広島県三原市の公衆浴場施設で起きたレジオネラ症集団感染事例において、現地の三原市で次のとおりご協力しました。
①行政の対応強化(職員研修会の開催、対策指針・対策事業の提案など)
②管内施設の衛生管理徹底(レジオネラ症対策講習会の開催、講習会後の個別相談など)
③事故発生施設への対応(現地調査・事故の原因究明の協力、改善方法の検討など)
(講師)
・2025年、石川県南加賀保健所、入浴施設衛生管理研修会「公衆浴場、旅館、ホテル等入浴施設のレジオネラ症対策」
・2025年、鹿児島市保健所、レジオネラ症感染防止研修会「入浴施設におけるレジオネラ症感染防止対策」
・2025年、港区みなと保健所、衛生講習会「レジオネラ症対策について」
・2024年、大分県 レジオネラ症発生防止対策研修会「入浴施設のレジオネラ症発生防止対策について」
・2024年、宮崎県・宮崎市、施設向け令和6年度レジオネラ属菌汚染防止対策講習会「公衆浴場・旅館・ホテル・福祉施設・医療施設等の入浴設備の衛生管理」
・2024年、(公財)青森県生活衛生営業指導センター、公衆浴場・旅館・ホテル等施設向けレジオネラ症発生予防対策研修会「レジオネラ症対策の基礎知識と入浴施設の衛生管理の方法」
・2022年、国立保健医療科学院、令和4年度・環境衛生監視指導研修で「環境衛生監視指導の実際、公衆浴場のレジオネラ症対策」(オンライン)
・2021年、高知県、令和3年度入浴施設におけるレジオネラ属菌汚染防止対策講習会・環境衛生監視員を対象とした現場研修会「循環式浴槽立入検査の実際について」
(学会)
・2024年、第83回日本公衆衛生学会総会で、「レジオネラ症対策現場研修会の公衆衛生人材育成の成果」を発表しました。
・2023年、日本防菌防黴学会・第50回年次大会で、「令和4年台風第15号による大雨被災地の泥から検出されたレジオネラ属菌について」を発表しました。
・2021年、日本防菌防黴学会・第48回年次大会(オンライン開催)で、「令和元年東日本台風(台風19号)被災地の泥から検出されたレジオネラ属菌について」を発表しました。
・2012年、第56回生活と環境全国大会で、「文京区における公衆浴場等シャワー水のレジオネラ症発生防止対策の成果」を発表し、最優秀賞を受賞しました。