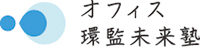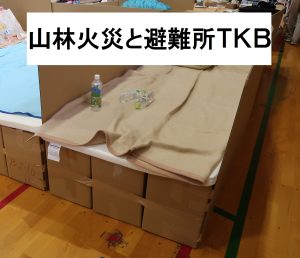【環監・保健師向け】レジオネラ・消毒の塩素濃度の上限
【消毒の塩素濃度の上限】
1 塩素濃度と水質基準
2 塩素濃度の測定法
3 プールと健康被害例
4 塩素濃度の上限の考え方
5 環監の視点(数値の根拠を説明できる)

こんにちは。元文京区文京保健所・環境衛生監視員で、『レジオネラ症対策のてびき』著(倉文明監修、一般財団法人日本環境衛生センター)、レジオネラ症対策・避難所衛生対策の研修講師をしている「オフィス環監未来塾」中臣昌広です。
2025(令和7)年2月~3月に、次のとおり、レジオネラ講習会・研修会の講師をつとめました。
① 2/7(金)鹿児島市保健所:*施設対象レジオネラ症感染防止研修会「入浴施設におけるレジオネラ症感染防止対策」
② 2/17(月)港区みなと保健所:施設対象令和6年度衛生講習会「レジオネラ症対策について」
③ 2/25(火)川崎市健康安全研究所:*職員研修会「公衆浴場・旅館・ホテル等のレジオネラ症対策」
④ 3/12(水)石川県南加賀保健所:*施設対象入浴施設衛生管理研修会「公衆浴場、旅館、ホテル等入浴施設のレジオネラ症対策」
*オンラインでの講師
質問で複数あがったのが、浴槽水の塩素濃度の上限についてです。
「残留塩素濃度は 2.0 mg/L 以上添加して問題ないか」「塩素濃度は、どのくらいまでが肌に影響がないのか」など質問がありました。
塩素濃度を考えるのは環監業務に有用ですので、今回は、「消毒の塩素濃度の上限」を考えます。
下記の記述は、国立保健医療科学院・生活環境研究部の小坂浩司氏、及び株式会社ヘルスビューティ・シニアテクニカルアドバイザーの藤井明氏、両氏のご意見を参考にしました。
1 塩素濃度と水質基準
(1)浴槽水
厚生労働省の「公衆浴場における衛生等管理要領」で、次のような記述があります。
<浴槽水の消毒に当たっては、塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻繁に測定して、通常0.4mg/L程度を保ち、かつ、遊離残留塩素濃度は最大1mg/L を超えないよう努めること>
0.4mg/L程度は、レジオネラ属菌を抑止するための数値です。
ちなみに、東京都の公衆浴場関係の条例は、平成15年以前、遊離残留塩素濃度が0.1mg/L 以上の基準でした。
大腸菌の殺菌を主な目的にしていたと考えられます。
では、最大1mg/L を超えないよう努めることとする根拠はどこにあるのでしょうか。
この文章を書いている段階で、浴槽水の塩素濃度の上限を最大1mg/L とする根拠を、公的文書で確認することはできませんでした。
推測できるのは、浴槽水が入浴者の皮膚にふれることから、皮膚に刺激がある、皮膚が敏感に反応して赤くなるなど、皮膚への影響を抑えるための数値ではないかということです。
(2)プール水
プールについて、厚生労働省の「遊泳用プールの衛生基準」の水質基準に記述があります。
<遊離残留塩素濃度は、0.4mg/L以上であること。また、1 .0mg/L以下であることが望ましいこと>
平成13年7月24日付「遊泳用プールの衛生基準に関する指針の一部改正に関する御意見の募集結果について」厚生労働省健康局生活衛生課のなかで、意見に対する回答(考え方)で次のような内容が書かれています。
<遊離残留塩素の上限値については、過剰な塩素投入を抑制するため設定されているものですが、1.0mg/Lを超えても直ちに健康被害を及ぼすものではありません>
(3)水道水
水道水について、水道法施行規則第17条第1項第3号の規定にあるのは、次のとおりです。
<給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1mg/L(結合残留塩素の場合は、0.4mg/L)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、0.2mg/L(結合残留塩素の場合は、1.5mg/L)以上とする>
コレラや赤痢など経口感染症を防ぐため、最低限の塩素濃度が0.1あるいは0.2mg/L以上となっています。
上限は、書かれていません。
水道水の水質基準を補完する項目で、快適水質項目の目標値があります。
残留塩素は、1mg/L程度以下となっています。
おいしい水の観点からの数値と考えられます。
レジオネラ症対策、災害時・避難所の衛生対策など、ご質問、ご相談、講師ご依頼などお受けしています。お気軽にどうぞ。
2 塩素濃度の測定法
塩素濃度の測定は、いくつかの方法があります。
(1)DPD法
汎用されている測定法です。
市販されているほとんどのDPD試薬は、発色剤と緩衝剤とが合わさった1剤式です。
発色剤は、塩素と反応してピンク色になります。
緩衝剤は、pHを調整するものです。
試料の水10mL に試薬を加えてピンク色に染め、その濃淡で濃度を測ります。
測定器の前面に、濃度を比べるための色見本が貼ってあり、見本の色と合わせて、濃度を出します。
現場で手軽にできる方法として、広く使われています。
5秒程度の短い時間で、遊離残留塩素濃度を測ります。
時間の経過とともに、結合塩素ができて、色が濃くなる傾向になります。
比色板を使う目視のやり方とは別に、測定器の吸光光度計を使い、濃度を測る方法があります。
吸光光度計は、たとえば、DPD試薬で色がついた水試料を測定器に入れて光を当て、その透過した光の強さから濃度が表されるものです。
別ページに、温泉のDPD測定に関する解説があります。
(2)SBT法
試薬を加えると、水中の遊離残留塩素と反応し、青緑に発色します。
色の濃淡で濃度を測ります。
メーカーの説明文をみると、結合型塩素とは反応しないとされています。
(3)電極法
理論的に、色の干渉を受けずに、電気的な反応を基に塩素濃度を測定することができるとされています。
水に浸した二つの電極に電流を流し、電圧と電流の関係から塩素濃度を導くものです。
三つの電極を使うタイプもあります。
現場では、他の測定法との比較、測定器のメンテナンスが大切になります。
試薬を使わない利点があります。
DPD法やSBT法と比べると、機器が高価になるかもしれません。
(4)ポーラログラフ法
溶液中の二つの電極の間に、電圧を変えて電気を流し、電圧と電流との関係曲線ポーラログラムを作成して濃度を測る方法です。
循環ろ過の塩素濃度の管理装置として、ポーラログラフ法のセンサーが配管中につけられることがあります。
3 プールと健康被害例
(1)腰洗い槽
『学校における水泳プールの保健衛生管理』(平成21年5月15日発行、財団法人日本学校保健会)のP46に、塩素濃度にふれた記述がありました。
内容を理解すると、こうなります。
腰洗い槽では、遊離残留塩素濃度が50~100mg/L 程度と高い濃度なので、アトピー性皮膚炎など皮膚が過敏な生徒は使用を控えて、シャワーのみで体を洗うことが推奨されています。
最近では、シャワーで体を洗うことが多くなっていると思います。
(2)プール水
『学校における水泳プールの保健衛生管理』平成28年度改訂版の記述では、塩素が汚染物質と反応して刺激臭や目への刺激の原因となる可能性があるので、適切な濃度管理が大切とあります。
私の保健所・環境衛生監視員として経験した例を、ひとつご紹介しましょう。
80歳代の女性から、「8月に室内プールで泳いだあと、手や足、お腹、腰のあたりが湿疹のように赤くなりました」と相談がありました。
現場調査すると、プール水の塩素濃度は適切な0.6 mg/L でした。
ちなみに、文京区プール条例施行規則では、プール水の消毒の遊離残留塩素濃度について、0.4~1.0 mg/L と定められています。
私は、実際の塩素濃度より、使われた塩素剤の量が関係しているのではないかと思ったのです。
プールの設備担当者も、そこに着目しました。
調べると、2月の利用者が6,500人、8月の利用者が14,400人でした。
夏の利用者は、冬の2倍以上です。
夏の塩素の使用量は、利用者数に比例するように、冬の1.8倍でした。
前記の『学校における水泳プールの保健衛生管理』平成28年度改訂版の内容を踏まえると、多量の塩素がプール水の汚れと反応して皮膚への刺激になった可能性を否定できないと思います。
以前、資料を調べたとき、次亜塩素酸ナトリウムは、長期にわたって皮膚に接したとき、刺激による皮膚炎や湿疹になると理解しました。
塩素剤の量が増えることで、皮膚への刺激になる可能性もあると思えたのです。
4 塩素濃度の上限の考え方
浴槽水の遊離残留塩素濃度の上限 1.0 mg/L 以下が望ましいという、数値そのものは、水道水の快適水質項目の目標値が原点かもしれません。
プール水では、塩素の刺激臭や目などへの刺激を考慮して、1.0 mg/L 以下であることが望ましいとされています。
浴槽水とプール水は、利用者の皮膚に湯水が接するという共通点があり、同じ数値が採用されていると推測されます。
1.0 mg/L になると直ちに健康被害が起きるような根拠資料はなく、目安ということができるでしょう。
5 環監の視点(数値の根拠を説明できる)
営業者との信頼関係を築くには、数値の根拠を正確に説明できることが大切です。
浴槽水の残留塩素濃度について、「通常0.4mg/L程度を保ち」は、レジオネラ属菌対策の消毒として、最低限必要な濃度です。
上限の「遊離残留塩素濃度は最大1mg/L を超えないよう努めること」は、過剰な塩素投入を抑え、入浴者の皮膚、目などへの刺激を抑えて快適性を保つための目安となる濃度です。
環監として、数値の裏にある根拠をしっかり理解することで、自信をもった衛生指導・助言ができると思います。
レジオネラ症対策、災害時・避難所の衛生対策など、ご質問、ご相談、講師ご依頼などお受けしています。お気軽にどうぞ。
【ご案内】
【2025(令和7)年度講座】
2025(令和7)年度のオフィス環監未来塾の講座一覧表をご覧いただけます。
『レジオネラ症対策のてびき』の概要はこちらから確認できます。ご購入をお考えのかたも、こちらから注文ができます。
・環監業務の悩み、課題がありましたら、ご相談をお受けしています。
・課題の解決につながる講座をご用意しています。
・保健師の皆様への研修のご相談、避難所の衛生対策活動等のご相談をお受けしています。
月に数回、環監のための、レジオネラ症対策、防災、仕事術、講座情報など、最新情報をメールで真っ先にお届けします。ご希望される場合、こちらにご記入ください。
【実績】
(書籍)
・2022年、厚生労働省のレジオネラ対策のページに掲載されている「入浴施設の衛生管理の手引き(令和4年5月13日)」の作成ワーキンググループのメンバーに、国立感染症研究所・倉文明先生らと共になっています。
・2013年、『レジオネラ症対策のてびき』倉文明監修(一般財団法人日本環境衛生センター)を出版しました。
(活動)
・2017年、広島県三原市の公衆浴場施設で起きたレジオネラ症集団感染事例において、現地の三原市で次のとおりご協力しました。
①行政の対応強化(職員研修会の開催、対策指針・対策事業の提案など)
②管内施設の衛生管理徹底(レジオネラ症対策講習会の開催、講習会後の個別相談など)
③事故発生施設への対応(現地調査・事故の原因究明の協力、改善方法の検討など)
(講師)
・2024年、宮崎県・宮崎市、施設向け令和6年度レジオネラ属菌汚染防止対策講習会「公衆浴場・旅館・ホテル・福祉施設・医療施設等の入浴設備の衛生管理」の講師をつとめました。
・2024年、(公財)青森県生活衛生営業指導センター、公衆浴場・旅館・ホテル等施設向けレジオネラ症発生予防対策研修会「レジオネラ症対策の基礎知識と入浴施設の衛生管理の方法」の講師をつとめました。
・2022年、国立保健医療科学院、令和4年度・環境衛生監視指導研修で「環境衛生監視指導の実際、公衆浴場のレジオネラ症対策」(オンライン)の講師をつとめました。
・2021年、高知県、令和3年度入浴施設におけるレジオネラ属菌汚染防止対策講習会・環境衛生監視員を対象とした現場研修会「循環式浴槽立入検査の実際について」の講師をつとめました。