【環監・保健師向け】災害時の衛生・集合住宅のトイレ問題
【災害時の衛生・集合住宅のトイレ問題】
1 災害時に1階のトイレが溢れる
2 配管を図面、現場で確認・点検する
3 災害時のトイレ点検の流れ
4 災害用トイレの資料
5 バケツ排水と感染症
6 環監の視点(感染症の視点をもつ)

元文京区文京保健所・環境衛生監視員で、『災害時・避難所の衛生対策のてびき』著(根本昌宏監修、一般財団法人日本環境衛生センター)、避難所の衛生対策・レジオネラ症対策の研修講師をしている「オフィス環監未来塾」中臣昌広です。
2025(令和7)年6月下旬、災害用トイレのオンライン勉強会(主催:株式会社イオタ)に参加しました。
株式会社イオタは、東京都の委託を受けて、都内の自主防災組織等対象の「東京防災学習セミナー」開催の実績がある会社です。
講師は、コンサルタントで、空気調和・衛生工学会で「集合住宅の『災害時のトイレ使用マニュアル』作成手引き」の作成に携わった木村洋(きむら・ひろし)氏です。
勉強会には、防災関係者10人以上のかたが参加しました。
勉強会で私が理解した内容をご紹介します。
勉強会では、主に集合住宅のトイレ問題を考えました。
なお、自治体により、集合住宅は、災害時に建物被害が小さいとき、在宅避難が基本とされています。
1 災害時に1階のトイレが溢れる
勉強会では、講師が解説したNHKテレビ番組、マンションのトイレ排水管の実験の映像が流れました。
地震で、1階の排水管が変形したと想定しました。
上階から、トイレの水を流しました。
1階のトイレは、4回目の上階からの排水で便器内の水が動きました。
その後の排水で、汚水が逆流して、1階トイレから空気と排水が出てきました。
集合住宅では、1階の排水管の損傷により、上階からの排水があると、1階のトイレが溢れることがわかりました。
2 配管を図面、現場で確認・点検する
現場での確認・点検は、集合住宅居住者の専門家、あるいは外部の専門業者等の協力が必要です。
図面をたよりに、設備を点検していきます。
(1)排水設備
排水設備のチェックポイント箇所の例は、次のとおりです。
①排水縦管:上階から下階、下水へ向かう管
②排水横主管:同じ階の横の配管
③第一枡:下水管へ出る前、建物・敷地内の排水が集まる箇所
④汚水槽:地下階の汚水をためる槽
⑤ディスポーザー処理槽:もっている場合に確認・点検
(2)給水設備
①受水槽:1階や地下階、屋外にある水道水をためるタンク
②高置水槽:屋上にあり、受水槽から運ばれた水をためるタンク
最近では、マンションで、受水槽や高置水槽をもたない直圧増圧給水方式が使われるケースが多くあります。
水道本管からの水を、敷地内に設置したポンプで増圧して、上階へ運ぶやり方です。
過去の災害で、停電で増圧ポンプが止まったときに、水道本管の圧力で上階まで水が上がったケースがあると聞きました。
3 災害時のトイレ点検の流れ
トイレ点検は、集合住宅が居住可能と判断されていることが前提になります。
次の点検中は、各住戸で、携帯トイレを便器に設置して使用することが必要です。
(1)漏水チェック
建物内の、配管が見えるPS(パイプスペース)で、縦管に漏水がないかを確認します。
漏水がない場合、次のステップにいきます。
(2)敷地内の桝での確認
前記で、第一枡は、下水管へ出る前、敷地内で排水が集まる箇所と説明をしました。
この桝を確認します。
①液状化で桝が浮き上がっているとき →使用不可
②液状化で桝に泥がたまっているとき →使用不可
③トイレットペーパーを置き、流れたとき →使用可能(次の(3)を参照)
(3)桝が使用不可ではない場合、水を流してみる
①上階からバケツで水を流します
②1階のトイレで、空気の水はねがあると、水漏れの兆候になります。次に便器があふれます。使用が難しい状況です。
③桝にトイレットペーパーを置いて、半日後に流れていれば使用可能です。
(4)水道復旧時の確認
①台所や洗面所で、通水してみます。
②トイレは、最後に通水をします。なぜなら、空気が入ると故障の原因となる可能性があるからです。
③トイレは、ロータンクから所定の水量で流します。バケツによる水流しは、流れない事例がありました。
4 災害用トイレの資料
(1)東京トイレ防災マスタープラン
東京都では、令和7年3月に『東京トイレ防災マスタープラン』を発行しました。
こちらのURLから、プランの詳細を見ることができます。コピーして検索してください。
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1030489/index.html
目次には、災害時のトイレの被害、フェーズに応じた主な災害用トイレの使用可否、災害用トイレの確保などがあります。
後半で、「区市町村における災害時のトイレ確保・管理計画の指針」が掲載されています。
プランのP27に、マンション防災のマンション管理組合の記述に、講師の木村洋氏が作成に携わった「集合住宅の『災害時のトイレ使用マニュアル』作成手引き」が参考として載っています。
(2)集合住宅の「災害時のトイレ使用マニュアル」作成手引き
「集合住宅の『災害時のトイレ使用マニュアル』作成手引き」のpdfは、木村洋氏のホームページで見ることができます。
「木村洋 災害用トイレ」で検索すると、「木村洋災害用トイレコンサルタント」のページがヒットします。
(3)災害時のトイレ対策
東京都下水道局・災害時のトイレ対策について
「排水設備 防災ハンドブック ~大震災に備えるために~」pdfを見ることができます。
こちらのURLから、詳細を見ることができます。コピーして検索してください。
https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/living/takuchi/toilet_disaster
(4)動画「災害時のトイレ、どうする?」
国土交通省ホームページに「災害時に使えるトイレ」ページがあります。
動画「災害時のトイレ、どうする?」(約15分)を見ることができます。
こちらのURLから、詳細を見ることができます。コピーして検索してください。
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000411.html
5 バケツ排水と感染症
(1)バケツ排水のやり方
災害時に、断水していても、下水道の損傷がほとんどなく、トイレの排水を流せるケースがあります。
そのとき、バケツの水を便器にあけて、排泄物を流すことがあります。
バケツの水は、3リットルくらいでしょうか。
ぼこぼこ音がして流れていけば、流れた証拠になります。
通常と違い、バケツ排水後、便器の水位が下がります。
便器内に水が見えないときは、コップで水を入れて配管内に封水をつくり、臭いが上がってこないようにします。
(2)バケツ排水と感染症
バケツ排水について、能登半島地震の被災地で、問題点を感じた医師がいました。
発災当初、避難所のひとつは、プールの水をバケツリレーで運んで使い、トイレを流していました。
しかし、トイレ内に水が散るため、ポリ袋に凝固剤を入れるやり方に変えたのです。
バケツ排水により、水とともに排泄物が便器まわりに飛び散ると、履き物や手、衣服に付いて、ノロウイルス感染症の発生や感染拡大につながる可能性を感じたのだと思います。
家庭用トイレで見られる、便器の奥に置かれて水をためるロータンクがあれば、ロータンクの中に水をためる方法がいいでしょう。
ロータンクに水を入れたあとは、通常どおり、レバーを倒して水を流せば、トイレを排水することができます。
6 環監の視点(感染症の視点をもつ)
災害時の集合住宅のトイレの使用可否については、点検の流れを日常に確認しておくことが必要でしょう。
集合住宅の防災訓練に、組み込んでおきたい項目ですね。
環監として、衛生対策や感染予防対策の視点から、災害時にトイレのバケツ排水が適切かを判断する場面があるかもしれません。
感染症発生や感染拡大の恐れを感じるとき、バケツ排水をやめて、ロータンクを使った排水、携帯トイレや簡易トイレの活用などの選択肢を検討してもいいでしょう。
災害時の衛生対策、避難所・避難生活の衛生対策のご質問、ご相談など、お気軽にお問い合わせください
災害時の衛生対策、避難所・避難生活の衛生対策の講師ご依頼につきまして、お気軽にお問い合わせください
『災害時・避難所の衛生対策のてびき』ご購入をお考えのかたは、こちらから注文ができます。
【ご案内】
【2025(令和7)年度講座】
2025(令和7)年度のオフィス環監未来塾の講座一覧表をご覧いただけます。
・環監業務の悩み、課題がありましたら、ご相談をお受けしています。
・課題の解決につながる講座をご用意しています。
・保健師の皆様への研修のご相談、避難所の衛生対策活動等のご相談をお受けしています。
月に数回、環監のための、レジオネラ症対策、防災、仕事術、講座情報など、最新情報をメールで真っ先にお届けします。ご希望される場合、こちらにご記入ください。
【活動実績】
(本・図書・出版物)
・2025年、介護保険専門紙『シルバー新報』(環境新聞社)で「介護現場のBCP 災害時の知識」を連載中です。
・2025年、月刊誌『クリンネス』(イカリホールディングス株式会社)で「衛生視点で感染症・災害時のBCPを考える」を連載中です。
・2022年、本『災害時・避難所の衛生対策のてびき』根本昌宏監修(一般財団法人日本環境衛生センター)を出版しました。
・2021年、専門誌『生活と環境』(一般財団法人日本環境衛生センター)で「災害時の居住環境 ~保健所・環境衛生監視員の視点から~」を連載しました。
・2020年、『災害時の保健活動推進マニュアル』(日本公衆衛生協会・全国保健師長会、令和2年3月)で「生活環境衛生対策」(避難所の環境衛生管理アセスメント)を分担執筆しました。
(活動)
被災地の地元自治体に協力して避難所の衛生対策活動・調査をしました。
・2024年、能登半島地震(石川県、珠洲市、七尾市)
奥能登豪雨(石川県、珠洲市)
・2019年、令和元年台風19号(長野市、いわき市)
・2018年、西日本豪雨(倉敷市)
・2016年、熊本地震(熊本市)
・2011年、東日本大震災(気仙沼市)
(調査活動)
・1995年、阪神・淡路大震災
(講師)
・2025年、神奈川県公衆衛生協会平塚支部講演会「災害時の公衆衛生活動、~災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策、保健所・環境衛生監視員の視点から~」
・2025年、豊田市役所研修「災害時の避難所等における衛生対策に関する研修」
・2025年、豊橋市保健所研修会「災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策 ~避難生活で健康を守るポイント~」
・2025年、日本災害食学会・災害食専門員研修会「災害時の水の安全・衛生」
・2024年、神奈川県公衆衛生学会「シンポジウム・避難所における健康危機管理」
・2024年、宮城県気仙沼圏域研修「災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策 ~保健所・環境衛生監視員の視点から~」
・2024年、宮城県登米地域災害対応研修「災害時における環境衛生対策」
・2024年、愛知県看護協会・研修会「災害時の生活環境衛生対策の課題と実際」
・2024年、福井県嶺南地域保健・福祉・環境関係職員研修「災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策 ~保健所・環境衛生監視員の視点から~」
・2024年、鳥取県市町村保健師協議会研修会「災害時の避難所・避難生活の衛生・感染予防対策 ~保健所・環境衛生監視員の視点から~」
・2024年、全国保健師長会、能登半島地震関連・緊急オンライン研修会「地震断水時の避難所・避難生活の衛生対策」
・2023年、令和5年度 兵庫県・北播丹波ブロック市町保健師協議会・研修会「災害時の避難所の衛生、感染症対策」
・2023年、第54回 沖縄県衛生監視員研究発表会及び研修会・特別講演「災害時・避難所の衛生対策について」
・2022年、国立保健医療科学院、令和4年度 住まいと健康研修「災害時の公衆衛生活動」(オンライン)
・2022年、東京都特別区職員研修所、令和4年度専門研修「地域保健」(主に保健師対象)「災害時の避難所の衛生・感染症対策、保健所・環境衛生監視員の視点から」
(学会)
・2025年、第30回日本災害医学会総会・学術集会「サーモグラフィ画像を活用した避難所の環境衛生管理」
・2025年、第52回建築物環境衛生管理全国大会「能登半島地震被災地の公衆衛生活動者を支援するためのIT活用の成果」
・2023年、日本防菌防黴学会・第50回年次大会「令和4年台風第15号による大雨被災地の泥から検出されたレジオネラ属菌について」
・2021年、日本防菌防黴学会・第48回年次大会(オンライン開催)「令和元年東日本台風(台風19号)被災地の泥から検出されたレジオネラ属菌について」
・2021年、第48回建築物環境衛生管理全国大会(オンライン開催)「令和元年東日本台風(台風19号)被災地の避難所の施設・空気環境の実態」奨励賞受賞
・2020年、第79回日本公衆衛生学会総会(オンライン開催) 「令和元年台風19号被災地の避難所における空気環境等の実態」
・2012年、第39回建築物環境衛生管理全国大会「東日本大震災被災地の避難所の施設・空気環境の実態」最優秀賞受賞
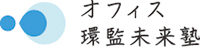


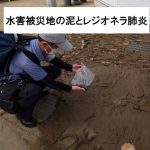

_page-0001-1-150x150.jpg)

